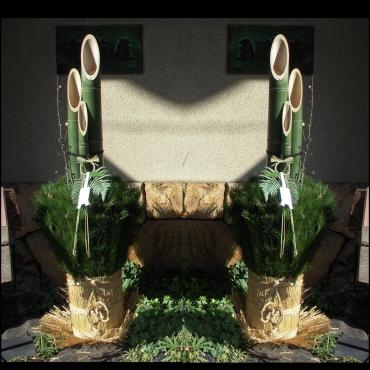さて恋人たちにとってXmasはやはり特別な日。
愛の告白、プロポーズをXmasに、と考えている男性諸君も多いのではないでしょうか。
そんな求愛の時に欠かせないのが赤いバラの花束ですね。
ではなぜ赤いバラを愛の告白に贈るのでしょうか?
日本古来の習慣ではな、く西洋から伝播された概念であることから西洋の歴史に基づいていることは想像できます。
バラ自体ははるか昔、メソポタミヤ文明のころには祭事用などに利用されていたそうです。
それが愛を象徴的する花になったのはキリスト教の影響が大きいようです。
聖母マリアの象徴は白いユリと棘のない白いバラ。一般には白いユリが有名ですがカトリックでは白いバラも象徴とされています。
これは聖母マリアの純潔、清らかで汚れない愛を表しています。
ではキリスト教において赤いバラの象徴はなんでしょうか?有名なマリア・マグダレナ。「マグダラのマリア」です。
イエスに前非を許された彼女の流した痛悔の血の涙が赤いバラの象徴で、その罪を洗い流した愛を象徴していると言われています。
聖母マリアの白いバラとマグダラのマリアの赤いバラ、それぞれ象徴される愛の中身が違うのですね。
聖書言語のギリシャ語には4つの愛を表す言葉アガペー、フィレオ、ストルゲー、エロスがあるといいます。
いわゆる男女間(恋人間)の愛、お互いを求める愛情はエロスに相当するのだと思いますが、このマリア・マグダレナの象徴である赤いバラがなぜ愛の告白、通じてエロスに関連付けられたかを記した明確な文献や資料は見つけられなかったのですが想像するに、男女間という人間として生々しい感情や欲情を、人として罪を背負い、許されることで血の涙を流した、マリア・マグダレナという生身の人間像に重ねたように思えます(私の解釈ですのでご容赦ください)
また赤=血の色であり、生きることそのもの、血の暖かさ、肉体的な意味での感覚、などがやはり男と女の関係に添った生身のイメージだったのだと思います。
無原罪の御宿りでイエスを生む聖母マリアと、その比較対象としても捉えることのできる、あまりに生身の人間的なマリア・マグダレナの存在。白と赤のバラが象徴とされる二つの愛、亜使徒としてイエスに従ったマリア・マグダレナに思いをはせると、このXmasに贈られる赤いバラのプレゼントもまた深い意味を持っているように思えてきます。
 東京都内フラワーギフト専門の花キューピット店(お花屋さん)の公式サイトです
東京都内フラワーギフト専門の花キューピット店(お花屋さん)の公式サイトです